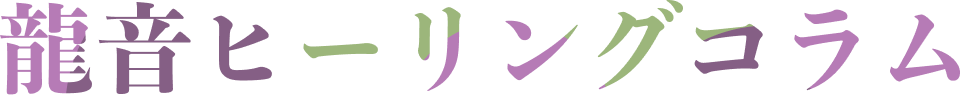歴史と祈りが息づく城下町の守り神—盛岡八幡宮
更新日:2025-07-03
神社仏閣
南部藩の総鎮守として
盛岡八幡宮は、延宝八年(1680年)に第二十九代南部重信公により建立された岩手県盛岡市の代表的な神社です。ご祭神は第十五代応神天皇である品陀和気命(ほんだわけのみこと)。農業・工業・商業・学問・衣食住など、人の営みすべてを支える神として、長く地域の人々に信仰されてきました。明治十七年の盛岡大火などによる度重なる災害を経て、現在の社殿は平成九年(1997年)に再建されました。朱塗りの大社殿と鮮やかな彫刻が印象的で、堂々とした風格を漂わせています。
十二の社を巡る信仰
盛岡八幡宮の魅力のひとつは、本殿のまわりに点在する多くの摂末社です。境内には「天神社」や「稲荷神社」「山神社」など十二社が祀られており、それぞれに学業成就、商売繁盛、家内安全などのご利益があります。これらを順に参拝する「十二社詣(じゅうにしゃもうで)」は、古くから城下町の人々の間で親しまれてきた信仰のかたちであり、今でも多くの参拝者が御朱印帳を片手に境内を歩いています。
縁を結ぶ「赤い結び紐」
境内には「縁結美神社(えんむすびじんじゃ)」と呼ばれる摂社もあり、良縁や恋愛成就を祈願する方々の人気を集めています。特に「赤い結び紐」を使って願いを託す独自の参拝スタイルが特徴的です。参拝者は、社殿前に用意された紐を結びながら、恋愛や人間関係、人生の良き出会いへの願いを込めます。この「赤い紐」は、神前結婚式で行われる「結い紐の儀」ともつながり、神と人、人と人をつなぐ象徴としての役割を果たしています。
勝負運を支える祈願所
学業成就や試験合格、スポーツでの勝利などを願う人には「天神社」や「勝馬神社」への参拝が人気です。特に、盛岡八幡宮では例祭の際に流鏑馬(やぶさめ)神事が行われることもあり、古来より馬と勝負運の関係が強く意識されています。その背景から、勝負事に関わる多くの人々が勝運祈願の場として訪れ、心を整えています。祈りの種類に応じて神様を選び参拝することができるのは、盛岡八幡宮ならではの特色といえるでしょう。
街に寄り添う祈りの拠点
盛岡八幡宮は「岩手県下一の大社」とも称され、市民の生活に深く根ざした存在です。人生の節目における神前結婚式、お宮参り、七五三、年始の安全祈願など、多くの人がこの地で神様と向き合い、自身の歩みを新たにしています。市街地からのアクセスも良好で、観光の合間にも立ち寄りやすい立地です。朱塗りの社殿と静かな森がつくり出す神域に身を置くことで、心身がすっと整う感覚を覚えるでしょう。祈りが日常とつながる場所として、盛岡八幡宮はこれからも多くの人の心の支えとなっていくはずです。